Loading...
Loading...
投稿日:2025年06月30日
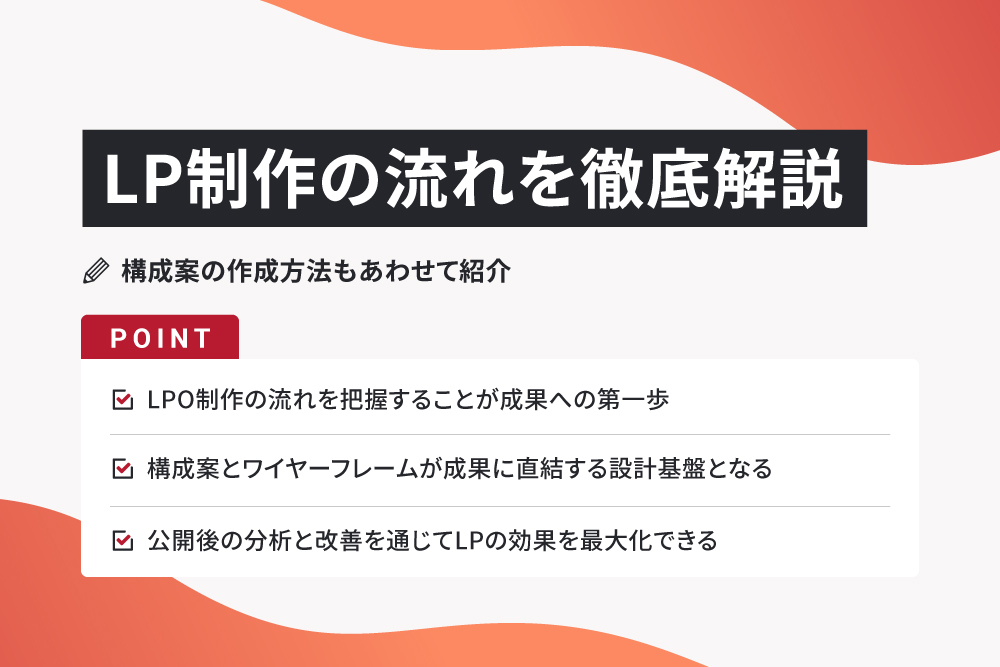
LP制作で成果を出したいなら、全体の流れを理解し、戦略的に設計することが重要です。
やみくもにデザインや文章を作っても、ターゲットに刺さるページにはなりません。ヒアリングから始まる制作の流れを一つひとつ丁寧に設計することで、成約率の高いLPが完成します。
本記事では、LP制作の正しい進め方を8ステップで紹介します。さらに、成果に直結する構成案(ワイヤーフレーム)の作成方法やLP制作をスムーズに進めるためのポイントも解説します。この記事を読めば、LP制作の全体像と正しい進め方がわかるでしょう。
LP制作をどの会社に依頼するか迷っている方は「株式会社ロックビル」がおすすめです。
▼この記事でわかる内容
・LP制作の流れを8つのステップで解説
・LP制作を進める上で必要な要素
・LP制作の流れを決めるワイヤーフレーム作成の方法
・LPを制作する3つの方法
・LP制作の流れをスムーズに進めるためのポイント
株式会社ロックビルは、ランディングページ制作のプロ集団です。ランディングページ制作の実績は800件を突破しており、成果につながるLPを作成可能です。
ロックビルでは、リード獲得に強いランディングページを設計・制作できます。デザインがどんなに優れていても、集客できなければ売上は増えません。
無料相談では、ランディングページのことなら何でも相談可能です。LP制作を検討している方は、お気軽にご相談ください。

LP制作では、見た目や文章の前に「戦略的な流れ」が成功を左右します。単なる作業工程ではなく、構成・訴求・検証までを一貫して設計する必要があります。
この章では、LP制作の流れを8つのステップに分けて具体的に解説します。
▼LP制作の流れを8つのステップで解説
・STEP①|ヒアリング・要件定義
・STEP②|企画書・リサーチ
・STEP③|構成案(ワイヤーフレーム作成)・ライティング
・STEP④|デザイン作成
・STEP⑤|コーディング・実装
・STEP⑥|テスト・確認
・STEP⑦|公開・納品
・STEP⑧|分析・改善提案
まずは、LP制作の方向性を定めるために、ヒアリングと要件定義を行います。
初期段階で目的やターゲット像が曖昧なまま進行すると、構成・ライティング・デザインに一貫性が生まれません。
最初に確認すべき要素は、LPの目的です。問い合わせ獲得、販売促進、イベント申込など、成果目標に応じて構成全体が大きく変化します。
続いて、想定するターゲットの属性や行動特性を具体化します。年齢、職業、検索意図、比較検討の基準、決定時の心理などを深掘りすることが重要です。
ヒアリング内容は要件定義書にまとめて共有します。目的やターゲット像、コンテンツ、スケジュールなどを明確に記載しましょう。
2つ目のステップでは、企画設計とリサーチによって構成の軸を固めます。
表面的なデザインや文章だけで構成を進めても、ユーザーの心は動きません。ターゲットの行動や心理、競合の打ち出し方、検索ユーザーの意図などを徹底的に調査しましょう。
検索エンジン経由の流入を増やすには、キーワードのリサーチも不可欠です。ターゲットが検索しそうな語句や検索意図、競合性の高いワードなどを整理し、構成案(ワイヤーフレーム)に反映させましょう。
リサーチと企画に十分な時間をかけることで、説得力のあるLPを制作できます。
3つ目のステップは、ページ全体の構成を設計し、ライティングの方向性を定める工程です。情報をどの順番で伝えるか、どのように配置すれば意図が正しく伝わるかを設計します。
構成案では、ページ冒頭からクロージングに至るまでの情報の流れを設計します。訪問者が内容をスムーズに理解できるよう、各要素を論理的に並べることが重要です。
その後、ワイヤーフレームを使って構成を視覚的に整理します。設計段階ではデザイン性よりも、情報の配置や伝わりやすさを優先しましょう。
ライティングでは、見出し・本文・ボタン文などを構成案に沿って作成します。
ライティング工程は、構成・デザインとの整合性を確認しながら進めることが大切です。適切なボリューム、読みやすい改行、情報の整理なども意識しましょう。
4つ目のステップは、構成案とワイヤーフレームをもとに、デザインを具体化する工程です。
デザインでは、装飾性だけでなく、構成に沿った情報の伝達力が求められます。視認性、導線、トーンを整えながら、ユーザーの感情と行動を導くビジュアルを設計します。
完成したデザイン案は、必ず社内で確認を行いましょう。構成との整合性、文言の正確さ、雰囲気の方向性などをチェックし、必要があれば修正依頼を出します。
デザイン工程は調整が発生しやすい工程なので、あらかじめ余裕を持ったスケジュール設定が重要です。
5つ目のステップは、構成とデザインをもとにページを構築する工程です。制作したデザインをもとに、ブラウザやスマートフォンで正しく表示されるようにコードを書いていきます。
実装フェーズでは、見た目だけでなく、読み込み速度や操作の快適さにも配慮する必要があります。クリックやスクロールの感覚、画像の読み込みタイミングなども、ユーザー体験を大きく左右する要素です。
中でも注意すべき点は、スマートフォンでの表示最適化です。アクセスの多くがモバイルからである現状では、PC表示に問題がなくてもスマホで崩れていれば大きな機会損失につながります。
コーディングと実装は、LPの最終的な完成形を生み出す工程です。目に見える部分だけでなく、裏側の処理も丁寧に整えることで、信頼性と使いやすさを両立させたLPが完成します。
6つ目のステップは、公開前のテストと動作確認を行う工程です。LPが正しく表示され、操作性や表示速度にも問題がないかを細かく検証します。
まず確認すべきは、各デバイスとブラウザでの表示状況です。PC、スマートフォン、タブレットの主要環境で、レイアウトや画像、文字サイズが崩れていないかをチェックします。
次に、リンクやボタンが正しく動作しているかを確認します。リンク切れ、ボタンの反応遅延などがあると、ユーザーの離脱につながるため注意が必要です。
リリース直前のテスト工程で妥協をしないことが、後のトラブル回避と信頼構築につながります。
7つ目のステップは、LPの公開または納品作業を行うフェーズです。
制作が完了した時点ではまだ成果は得られず、公開して初めて効果検証が始まります。そのため、事前準備とチェック体制が非常に重要です。
公開後によくあるトラブルのひとつに、コンバージョン計測の不備があります。Googleアナリティクスやタグマネージャーの設置漏れ、イベント設定のミスが原因で、正確なデータが取れないケースがあるため注意が必要です。
納品や公開の際には、チェックリストを用意すると検証がスムーズになります。リンクの動作、レスポンシブ対応、ファーストビューの見え方、CTAのクリック可否などを一項目ずつ確認しましょう。
8つ目のステップは、LPを公開した後の分析と改善提案です。ページは作って終わりではなく、実際のユーザー行動に合わせて運用を最適化することで効果を高められます。
主な分析手法としては、Googleアナリティクスやヒートマップツールの活用が基本です。ページ内のどこが読まれているか、どのボタンが押されているか、どこで離脱が発生しているかを確認します。
改善を後回しにすると、CV率が徐々に下がる恐れがあります。月に一度は効果測定を実施し、優先度の高い改善点から対応しましょう。
社内に専任の担当者がいない場合は、分析レポートの提出や改善提案を行う運用代行サービスの導入も有効です。

成果につながるLPを作るには、構成や文章だけでなく、要素ごとの役割を理解したうえで設計する必要があります。LPでは、ファーストビュー、ボディ、クロージングの3つに大きく分けて設計するのが基本です。
この章では、LPに盛り込むべき要素について解説します。
▼LP制作を進める上で必要な要素
・要素①|ファーストビュー
・要素②|ボディ
・要素③|クロージング
ファーストビューは、訪問者が最初に目にする領域であり、LP全体の成果を左右する重要な要素です。
スクロールせずに表示される範囲内で、「何のページか」「誰に向けて何を提供するか」を明確に伝える必要があります。
アイキャッチは、ページ内で最初に視認される画像やビジュアルです。商品やサービスの価値を、視覚的に瞬時に伝えるための情報設計が求められます。
視覚の第一印象は、読み進めるかどうかの判断に直結します。ブランドの信頼感、世界観、ベネフィットの一部を瞬時に伝える設計が不可欠です。
キャッチコピーは、LP全体の第一印象を決定づける重要なテキスト要素です。ページを開いた瞬間に伝わるメッセージが、離脱を防ぎ、読み進める動機を生み出します。
ターゲットが抱える悩みや疑問に直結するワードを冒頭に配置すると、共感や関心を得やすくなります。抽象的な表現よりも、数値や具体的な名詞を使って言語化することで、説得力が高まります。
CTAボタンは、ファーストビュー内でアクションを促す要素です。「申し込む」「ダウンロードする」など、目的に応じた具体的な行動を促す文言が必要です。
ボタン文には、動詞を中心に構成された言い切り表現を使用しましょう。たとえば「今すぐ無料で体験する」「3日間限定で申し込む」といった形式が効果的です。
視覚的には、ページ内で最も目立つ色を使い、他要素と十分なコントラストを持たせる設計がおすすめです。
ボディは、LP全体の中核を構成する情報パートです。ファーストビューで関心を引いたあとの訪問者に対して、サービスの魅力や根拠を丁寧に伝える役割があります。
具体的な説明や第三者の評価を通じて、納得と信頼を形成し、行動へ導くための土台となります。
導入文は、ファーストビューから続く最初のテキスト要素であり、読み進めるかどうかを左右するパートです。
訪問者の関心を維持しながら、課題の明確化とサービスの必要性を自然に伝える構成が求められます。
専門用語の連発は避け、わかりやすく、スムーズに情報へ移行できる表現を選ぶことが理想です。導入がうまく設計されていれば、その後のサービス紹介にも説得力が生まれます。
商品・サービス情報は、LP内でもっとも詳細な情報を伝えるパートです。導入文で課題を提示したあとは、訪問者が求める具体的な解決策や特長をわかりやすく提示する必要があります。
機能の羅列に終始せず「どう役立つか」「どんな変化が得られるか」を軸に構成することが重要です。
単なるスペック紹介ではなく「自分にとって必要な理由」が明確になる構成を心がけましょう。
実績とお客様の声は、第三者の評価を通じて信頼を高め、行動を後押しするパートです。
自社からの情報発信だけでは説得力に欠ける場合でも、利用者の体験や企業実績を提示することで納得感が生まれます。
お客様の声は、実在する人物または企業のコメントを使って、利用の背景や成果を具体的に伝えることが重要です。許諾が得られる場合は、写真付きで掲載しましょう。
クロージングは、ページの最下部で訪問者に最終アクションを促すパートです。LPの構成がどれだけ優れていても、クロージングが不十分であればCVに結びつきません。
ページ全体を通じて信頼を積み上げたあと、迷わず行動に移せるよう設計することが重要です。
よくある質問(FAQ)は、読み手が抱える疑問や不安を事前に解消するための情報設計です。読み進めた読者が最後の一歩を踏み出す際、判断材料として機能します。
設計のポイントは、対象ユーザーの立場や知識レベルを前提に、想定される不安を言語化することです。
FAQを充実させることで、情報の透明性が高まり、安心してアクションを起こすきっかけが生まれます。
問い合わせフォームやCTA(Call To Action)は、訪問者に最終的な行動を促す要素です。
LP全体の構成がいくら優れていても、アクション導線に不備があれば成果にはつながりません。情報提供だけで終わらせず、行動まで導くための設計が不可欠です。
行動を後押しする設計と配慮が、成果につながるフォーム設計の鍵となります。
ワイヤーフレームとは、構成案をベースにして要素の配置や導線を可視化した設計図です。装飾や色味は含まず、情報構造とコンバージョンへの流れを論理的に整理する目的があります。
ここからは、ワイヤーフレーム作成時に押さえるべき5つのステップを順に解説します。
▼LP制作の流れを決めるワイヤーフレーム作成の方法
・STEP①|ファーストビューの設計
・STEP②|導入パートで興味を引く
・STEP③|説得力を裏付ける証拠を配置
・STEP④|信頼性を高める要素を挿入
・STEP⑤|クロージングとアクションの導線設計
まずは、ファーストビューの設計から始めます。ファーストビューとは、LPを開いた瞬間に画面上に表示される最初の要素です。
ファーストビューでは「誰に向けた」「どんな価値を提供する」サービスかを端的に伝える必要があります。
興味を引くキャッチコピーや直感的に伝わるアイキャッチ、明確なベネフィットを記載しましょう。
最初の数秒で心をつかめるかどうかがLPの成果を大きく左右するため、ファーストビューは丁寧に設計することが重要です。
2つ目のステップは、導入パートの設計です。ファーストビューで興味を持った訪問者に対し、本文へスムーズに誘導する役割を担います。
導入で重視すべきは、ターゲットの課題を正確にとらえることです。具体的な困りごとや悩みを示し、それに対して商品やサービスがどのように役立つかを端的に伝える構成が効果的です。
導入パートの段階で冗長になりすぎると、読了率が低下します。内容はコンパクトにまとめましょう。
3つ目のステップは、訪問者の納得感を高めるための証拠を効果的に配置することです。
サービスや商品の魅力を伝えるだけでは信頼は得られません。実績やデータなど、根拠を明示することで説得力が大きく向上します。
主張だけを並べるのではなく、第三者視点での評価や検証結果をもとに構成しましょう。
4つ目のステップは、訪問者の不安や疑問を軽減し、信頼を高める情報を盛り込むことです。
発信者目線の情報だけでは、読み手の不安は払拭できません。実際の利用者の言葉や外部からの評価があることで、納得感が生まれます。
また、返金保証・運用サポート・セキュリティ体制などの安心材料を加えることも重要です。安心して行動してもらうための工夫が、LPの完成度を左右します。
5つ目のステップは、クロージングとアクション導線の最適化です。
いくら魅力的な内容でも、行動へつながらなければ成果には結びつきません。読み終えたあと、スムーズに申し込みや問い合わせへ進める構成が必要です。
効果的なクロージングと導線設計は、CV率を左右する重要な要素です。行動までの流れが整理されているか、ファーストビューから最終セクションまでの一貫性があるかを確認しましょう。

LP制作は、どの方法を選ぶかによって、制作の流れや品質、納期、コストが大きく異なります。ここでは、LPを制作する3つの方法について解説します。
▼LPを制作する3つの方法
・方法①|LP制作ツールを活用して自社で内製する
・方法②|LP制作会社に依頼する
・方法③|フリーランスに依頼する
自社でLP制作を行う方法として、ノーコードやローコードのLP制作ツールを活用する手段があります。
代表的なツールには「ペライチ」「STUDIO」「Wix」などがあり、テンプレートを選び、要素をドラッグ&ドロップするだけで直感的に制作できます。
自社内製のメリットは、コストの低さとスピード感です。外注費がかからず、自社の担当者がその場で編集・反映できるため、A/Bテストの実施や文章の差し替えもスムーズです。
一方で、デザインの自由度やSEO設定の細かさには制限がある場合もあります。
また、制作にあたっては社内にある程度のWeb知識やライティングスキルが必要です。単に見た目を整えるだけでなく、ユーザー導線やコンバージョン設計を理解したうえで作業を進めなければ、成果にはつながりません。
社内にWeb担当者がいる、LPの本数が多い、PDCAを高速で回したいという企業にはおすすめの手段です。
LP制作会社への依頼は「自社にノウハウがない」「品質を重視したい」といった課題を抱える企業におすすめです。
構成案の設計からデザイン、実装、公開、分析までを一貫して任せられるため、プロの知見を活かしたLP制作が可能になります。
とくに強みとなるのは、マーケティング視点での戦略的な設計です。ユーザーの心理や導線を踏まえて構成を作り、視認性や訴求力を高めたデザインに落とし込むことで、成果に直結するLPが完成します。
LP制作をどの会社に依頼するか迷っている方は「株式会社ロックビル」がおすすめです。
株式会社ロックビルは、ランディングページ制作のプロ集団です。ランディングページ制作の実績は800件を突破しており、成果につながるLPを作成可能です。
ロックビルでは、リード獲得に強いランディングページを設計・制作できます。デザインがどんなに優れていても、集客できなければ売上は増えません。
無料相談では、ランディングページのことなら何でも相談可能です。LP制作を検討している方は、お気軽にご相談ください。
>>無料相談はこちら
LP制作の外注方法として、フリーランスの活用も効果的です。制作会社よりコストを抑えながら、専門的なスキルを持つプロに依頼できる点が魅力です。
対応範囲はフリーランスによって異なりますが、構成・デザイン・コーディングまで一貫して請け負うクリエイターも多くいます。
特定の工程だけを依頼したい場合にも柔軟に対応してもらいやすいため、自社リソースと組み合わせて進行したい場合に最適です。
ただし、やり取りの多くが個人間で進むため、契約書や納品物の定義などは明確に取り決めておきましょう。

LP制作を滞りなく進行するには、あらかじめ進行上の注意点や体制を整えることが重要です。ここでは、LP制作の流れをスムーズに進めるためのポイントを3つご紹介します。
▼LP制作の流れをスムーズに進めるためのポイント
・ポイント①|目的とゴール、ターゲットを明確にしてから着手する
・ポイント②|迅速なレスポンスを心がける
・ポイント③|LPに使用する素材を事前に集めておく
最初に決めるべきは、LPで達成したい目的です。リード獲得、資料請求、来店促進など、KPIに直結するゴールを具体化しましょう。
また、ターゲット像の明確化も重要です。年齢層、課題、行動傾向などを整理することで、コンテンツの設計や訴求の方向性がブレなくなります。
成果を出すLPをつくるには、最初の設計段階での戦略定義を丁寧に行いましょう。
LP制作では、制作チームとクライアント側の連携が多く発生します。
質問への回答や修正指示が遅れると、工程が滞り、全体の遅延につながります。社内の承認ルートや決裁者を明確にし、必要に応じて権限移譲も検討しましょう。
チャットツールやタスク管理ツールを併用すると、情報伝達が効率化されます。
信頼関係が築けると、相互に柔軟な対応ができ、トラブルも防ぎやすくなります。
素材の準備は、スムーズな制作進行に直結します。掲載画像、図版、サービス資料、ロゴなどをあらかじめ整理しておくことが求められます。
著作権の確認や、素材の加工が必要な場合はスケジュールに余裕を持たせましょう。
構成案の段階で素材の要否を見極め、優先度に応じて段階的に提供できる体制を整えておくとスムーズです。
LP制作をどの会社に依頼するか迷っている方は「株式会社ロックビル」がおすすめです。
株式会社ロックビルは、ランディングページ制作のプロ集団です。ランディングページ制作の実績は800件を突破しており、成果につながるLPを作成可能です。
ロックビルでは、リード獲得に強いランディングページを設計・制作できます。デザインがどんなに優れていても、集客できなければ売上は増えません。
無料相談では、ランディングページのことなら何でも相談可能です。LP制作を検討している方は、お気軽にご相談ください。
本記事では、LP制作の流れを8つのステップに分けて解説しました。制作工程を体系的に理解すれば、作業の優先順位や課題の早期発見につながります。
LP制作の成果を最大化するには、初期段階で目的やターゲットを明確に設定することが欠かせません。ワイヤーフレームでは情報整理に注力し、装飾よりも伝達のしやすさを重視しましょう。
全体の流れと各工程の目的を把握することが、高品質なLP制作の第一歩です。

【参考記事】
・LP(ランディングページ)とは?ホームページとの違いを徹底解説!|sober design
・LP(ランディングページ)の基本構成とは?制作会社しか知らない重要な要素と注意点
・LP制作のポイントと作る手順【CV率の高いLPを制作するポイントを全公開】
・ワイヤーフレーム活用術!LP制作の流れとポイントを解説|シンプリック